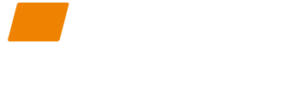経営戦略の要となる予実管理!具体的な手順と成功の秘訣を解説
目次
経営戦略の要となる予実管理!具体的な手順と成功の秘訣を解説
(新任予算ご担当者様向け)
 予実管理は、次年度の予算に対して一定間隔で実績と比較し、差が生じている場合はその原因を分析し対応策を講じる経営管理手法です。企業の経営目標を数値化した予算を達成、そして状況に応じた見直しを行うために行なわれます。
予実管理は、次年度の予算に対して一定間隔で実績と比較し、差が生じている場合はその原因を分析し対応策を講じる経営管理手法です。企業の経営目標を数値化した予算を達成、そして状況に応じた見直しを行うために行なわれます。
本記事では、予実管理の重要性や具体的な手順、成功するポイントについて解説します。また、なぜ予実管理が必要なのか、期待される効果、実務運用で直面する課題についてもお伝えします。
既に予実管理を行なっている企業では、資料をExcelで作成しているケースが多いかもしれません。Excelは誰でも使えて有用なツールである一方で、機能や容量には限界もあります。予実管理のための資料作成業務が属人化することを防ぎ、作業工数削減にもなる、予実管理に便利な専門システムもご紹介します。
1 企業にとって予実管理とは何か
第1章では、予実管理の概略、予実管理の意義、予実管理と予算管理との違いについて説明します。
企業目的を達成するために予実管理が必要であることは、大企業であろうと中小企業であろうと変わることはありません。企業の規模にかかわらず、予実管理は経営戦略の要となるものです。
1-1 予実管理とは

予実管理とは、予算と実績を比較分析し管理することで、予算実績管理の略称です。
企業では目的に応じて短期予算、中期予算、長期予算などさまざまな予算を立てています。予実管理で比較対象となる予算は、当期に達成可能な目標として策定された短期予算を主に使用します。
新年度がスタートすると、定期的に予算と実績を比較分析します。これによって、予算に対してどの程度の実績となっているかを把握します。分析を行った結果、予算通りの進捗となっていなかった場合、差異が発生している原因を明らかにして、対応策を検討します。対応策は関係者に周知徹底し、期内に目標予算が達成できるように促すとともに、乖離の理由が予算の抜本的な見直しを要するものであれば、その修正の要否も判断することを繰り返していきます。
1-2 予実管理の意義とメリット
経営戦略の要と言われる予実管理ですが、なぜ企業にとって予実管理が重要なのでしょうか。
予実管理を行う意義は、経営目標を達成することです。そのために予算と実績を比較し、予算と比べて実績が下振れしているのか上振れしているのか、振れ幅や金額はいくらぐらい乖離しているのかなど把握し、その原因を究明し、改善策を講じます。
予実管理を行う一番のメリットは、予算が計画通りに進捗しているかどうかが数値で可視化される点にあります。予実管理を行なっていなければ、予算と実績が乖離していても気付くことができません。その結果、改善策を講じるきっかけを失い、予算を達成できずに会計年度を終えることにもなりかねません。一方で、予実管理を行なっていれば、目標が達成できそうかどうか早い段階で気付くことができ、企業活動の軌道修正も可能になります。
また、上場企業の場合は、公表された直近の予想値と新たに算出された予想値に大幅に差異が生じた場合、その内容を開示することが義務付けられています。予想値は株価に重要な影響を与え、適正な情報開示がされていないと株主が損害をこうむる恐れがあります。そのため、上場企業ではコンスタントに予実管理が行なわれています。
1-3 予実管理と予算管理の違い
予実管理と似た経営用語に「予算管理」という言葉があります。予算管理とは、企業活動における予算に関わる管理活動のことを指します。予実管理も予算に関わる管理活動なので、この側面だけ見ると、予実管理と予算管理は同義で扱われる場合もあります。
予実管理と予算管理を区別して使用している企業では、予実管理を予算と業績との間の差異を明確にし、その原因を分析するプロセスとして捉えて、その過程を重視していることがあります。
どちらにしても、予算で目標を立てただけで検証しなければ意味がありません。予算は立てたら終わりではなく、実際の数値と比較して進捗度合いを把握したり、施策との整合性を確認したりすることが重要になります。
1-4 「経験と勘」からの脱却
経営者や業務担当者の過去の成功体験に基づく「経験と勘」に頼った事業活動は、事業環境や実態から乖離したものになってしまうリスクがあります。
変化のスピードが早い環境下では、企業の置かれている状況をタイムリーに数字で捉えることが重要です。その手法として、予実管理を取り入れることで、自社が予算通りの実績をあげられているか定量的に判断することができます。乖離が生じている時は差異分析をした上で、課題の抽出と対策の立案を行い、タイムリーに営業活動を軌道修正することができます。
また、経営者や一部業務担当者の「経験と勘」に依拠したあり方は、業務フローの属人化を脱却できていないことを意味します。業務フローの属人化を超え、フローの標準化を推進することなしに事業規模の拡大はありえないでしょう。
予実管理によるマネジメントを通じて、企業全体の価値向上に貢献する再現性のある企業活動を目指すことが可能になります。
1-5 予実管理表
予実管理表とは予実管理を行う分析資料を指します。この予実管理表は、どのような内容を記載し、どこまで詳細な数字を載せる必要があるのでしょうか。
予実管理表では売上、利益などが把握できることが必要です。また複数の事業、製品、拠点がある場合は、大まかな粒度では差異分析も難しく、原因を把握できるためにも、事業部単位、商品単位に分けた、予算と実績値のを集計が必要となります。
また、予算と実績を比較して分析を行うことから、予算と実績は同じ形式であることが求められます。一般的に、実績は損益計算書と類似の様式で作成されますので、予算も損益計算書と同様の形式で作成すると比較しやすくなります。
予実管理表では、損益計算書(予算)と損益計算書(実績)を単月・累積で比較し、差異を求める形で作成すると良いでしょう。この書式であれば、数値を一覧で把握できて、差異分析がしやすく、業務の弱点が分かり、どのような対策を講じたら良いのか具体的に考えることが可能になります。
予実管理表は、取締役会や営業会議などの資料として利用されるだけではなく、従業員にも適宜フィードバックし、今後の活動に活かすことが理想です。
2 予実管理の具体的フロー

第2章では、予実管理を行う時の具体的なフローについて解説します。フローは大きく分けて、予算目標の設定、実績値の入手、予算と実績の比較分析、予算修正の4プロセスに分かれています。
2-1 予算目標を設定する
まずは予算の編成から始めます。
予算の編成はなるべく具体的な数字を集めて策定することで、ブレが少なくなります。具体的な方法としては、外部環境要因なども視野に入れながら全社の事業目標を作成し、商品別や部門別など複数の視点で事業を細分化しておきましょう。細分化することで責任の所在が明らかになり、予実比較で差異が発生した場合の原因分析に利用できます。
さらに、各部門でプロジェクトを立ち上げている場合は、プロジェクトごとに目標を設定するとより精緻な売上の数字を得ることができますので、プロジェクトごとの予算も設定しましょう。
予算編成を行う方法としては、おおまかにトップダウン方式とボトムアップ方式があります。トップダウン方式は、経営者が予算計画を決め、それをもとにそれぞれの部門・プロジェクトごとに細かい予算設定を行う方式です。ボトムアップ方式は、それぞれの部門・プロジェクトごとに予算を設定し、全体の予算編成にしていく方式です。
トップダウンでもボトムアップでも、予算設定では経営層と現場が予算策定業務を通じてコミュニケーションを図り、社内のコミットメントの意識を醸成していくことが重要です。
2-2 月次決算を行う
 実績を振り返るために月次決算を行います。
実績を振り返るために月次決算を行います。
予実管理の目的は、差異が生じている商品や部門をいち早く見つけ、施策を練って、事業活動に活かすことで目標を達成することです。その趣旨から、なるべくタイムリーに課題を把握できるように、実績を確認できる書類の作成頻度を増やすと良いでしょう。リアルタイムに近い形で現場にフィードバックするためには、月次決算を行いながら予実管理を行うのが一般的です。業種、会社によっては日次・週次で行っている企業もあります。月次決算は、企業の現状を知る上で大変貴重な資料です。まだ月次決算を行っていない企業は、月次決算を行う体制づくりから着手しましょう。
具体的には、現預金残高を確認する、在庫の棚卸を行う、仮払金や仮受金の整理をするなど、本決算と近い手続きを経て月次決算書を作成します。月次決算書をどこまで準備するかは企業ごとの判断になりますが、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表について、予算実績対比表を作成する会社もあります。
手間がかかって大変だと思われるかもしれませんが、経営戦略の要になる重要な資料です。一気に全てを同時に進めようとすると却って開始時期を遅らせてしまう可能性があります。可能な範囲、粒度で始めて、徐々に濃度を深めていくやり方がスピード感もあり現実的、また効果的であることも少なくありません。
2-3 予算と実績を比較・差異分析する
 次に、予算と実績を比較し、差異分析を行います。
次に、予算と実績を比較し、差異分析を行います。
まず比較する対象は2種類あります。月別予算と月次決算の比較、そして期首から当月までの累計額での予算と実績の比較です。
大きな差異が発生している場合は、その原因を究明します。どの程度のものを分析するかの判断は、商品や金額、勘定科目によっても異なります。あまり細かい差異にとらわれ過ぎると、時間が掛かり過ぎて、タイムリーに現場に対策をフィードバックできなくなったり、大きな潮流を見逃してしまうこともあるので注意しましょう。分析の際は、部門別予算や商品別予算と実績との比較や、差異が発生している部門の担当取締役や現場責任者にヒアリングを実施します。
予算と実績は、部門単位や商品単位で売上や費用を集計して作成するため、期中で組織替えを行うと予実管理が難しくなります。予算と実績は、経理が把握している情報、事業部が管理している情報、子会社の情報など、さまざまな情報を元に集計されています。
子会社が多かったり事業内容が複数に分かれていたり期中に組織替えがあったりした場合には、スタンドアローンのExcelでは担当者の負荷が重くなり対応が難しくなることが予想されます。これらをマニュアルで対応していくには相当の困難を伴います。
2-4 軌道修正する
最後は、差異が発生した場合の予算の軌道修正についてです。
予算と実績を比較し差異分析を行った結果、原因がつきとめられた場合は、対策を検討します。差異の原因は、その企業にとっての経営課題そのものといえるものなので、原因の把握は予実管理の最重要のポイントとなるものです。この課題解決には、経営資源を費やして取り組みましょう。
また、原因が一時的な影響のものなのか、長期的な影響のものなのかで対応すべき施策が異なることになります。
原因に対して対処が難しい是正できない、または是正しても予算達成が難しいと判断された場合は、予算を修正することになります。なお、上場企業については、適時開示の判断基準を上回る差異が発生していた場合、業績予想の修正などに関する開示が必要となるため、予算の修正は避けられません。
差異分析をした結果、下振れすることもあれば上振れすることもあります。上振れしていた場合は、その分析によって自社の強みをあらためて把握することになり、より伸ばすための施策を検討することができます。
3 予実管理を成功させるためのポイント
予実管理は企業の課題を浮き彫りにし、当期の業績を左右する重要なマネジメントのひとつです。予算と実績をただ単に比較するだけで、何の戦略も立てないまま終わらせてしまっては、本来の機能を果たすことはできません。また、課題を見つけて対策を講じたとしても、従業員に対するフィードバックがなければ効果は望めません。
3-1 適切な予算を立てる
予実管理が成功するためのポイントのひとつに、適切な予算を策定するということが挙げられます。
予算を立てる際は、前期の実績に外的要因と内的要因を加味して算出するのが一般的です。外的要因としては、市場の状況、製品の売れ筋、景気の動向、近隣での他社の出店状況、競合他社の状況などがあります。内的要因としては、マーケティング活動の強化、新商品の開発、販売経路の拡大、人員配置の変更などがあります。外的要因と内的要因による影響を反映させた精度の高い予測に基づき、前期の実績をベースにして予算を立ててみると良いでしょう。
反対に不適切な予算の例として、経営者の意向で達成不可能な予算を立ててしまうことが挙げられます。その結果、各部門に無理な数字が押し付けられ、従業員にも過度な負荷がかかってしまう可能性があります。逆に、予算を保守的に見積もるケースでは事業活動の緊張感が緩み、従業員のモチベーションが下がってしまうこともあります。
3-2 部門ごとにKPIを設定する
 予算や実績は部門別・事業部別に把握されますが、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)も部門ごとに設定することで、予実管理の精度が向上します成功する可能性が高まります。
予算や実績は部門別・事業部別に把握されますが、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)も部門ごとに設定することで、予実管理の精度が向上します成功する可能性が高まります。
KPIの具体例を部門別、業種別に紹介します。部門別KPIとして、営業部であれば、商談数、成約率、新規顧客開拓数、平均顧客単価などが挙げられます。部門によっては、顧客満足度のような数値化できないものがKPIとして設定されるケースもあります。次に業種別KPIとしては、製造業であれば、製造原価率、歩留まり率、労働生産性などがKPIとして設定されます。
部門別のKPIを用いるメリットは、各部門の業績をその特質に合わせた指標に照らして客観的に評価することができる点です。また、各部門に所属する従業員にとっては、事業実態に応じた達成すべき目標が明確になり、ひいては企業の業績向上にもつながります。
また、KPIを定める際に問題になるのは、粒度をどの程度に設定するかということです。粒度を小さくすれば細かいKPIの設定ができますが、全体像がぼやけてしまうことがあります。更に多すぎるKPI も活動の焦点が曖昧になってしまう懸念があります。業務上コントロール可能な粒度にすることが重要です。
KPIは継続性も重要ですが、環境変化や、必ずしも事業実態を把握する上での指標として適切ではないと判断されたら、柔軟に見直すことも必要でしょうか。
予実管理でKPIを設定するメリットは、財務数値化しにくい業務内容についてもKPIの評価を元に指標化することができ、KPIの予実差異の分析を通じて、具体的な改善策を示すことができる点にあります。
3-3 PDCAサイクルを意識する
 予実管理を成功させるための3つ目のポイントは、PDCAサイクルを意識することです。
予実管理を成功させるための3つ目のポイントは、PDCAサイクルを意識することです。
PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」・「Do(実行)」・「Check(確認)」・「Action(改善)」の4つのステップからなるマネジメントサイクルです。
既に耳慣れた言葉かもしれませんが、予実管理ではこのPDCAサイクルを実践するか否かで、結果が大きく左右されます。実際に予実管理の中でどのようにPDCAサイクルを実践すれば良いのでしょうか。
「Plan」は、事前に目標や予算を設定することです。企業を取り巻く外的要因と内的要因による影響、前期の実績、前期に改善点として識別した項目、その後の改善度合いなども含めて、予算を立ててみましょう。
「Do」は、計画を実行に移すことです。日々の事業活動がこれに当たります。
「Check」は、予算と実績を比較し差異を認識し、原因を究明することです。計画よりも高く推移した場合は自社の強みをさらに強化する施策を考えます。一方で計画よりも低く推移した場合は、改善策を立てます。この段階がPDCAサイクルの中でも、最も重要になります。
最後に「Action」ですが、Checkで発見された課題や改善策を、日々の業務に取り込みます。
予実管理は、CheckやActionまでサイクルを回すことで、効果を発揮するようになります。
3-4 課題の洗い出しを行う
予実管理の本質的な目的は、予算と実績を比較し、差異が発生していれば原因を特定し、課題を見つけることです。予実管理は単なる数字の突き合わせではなく、数字の背後にある企業の課題を発見することこそ重要です。
課題が発生している場合は、なるべく早く発見してタイムリーに改善策を講じることが重要です。そのために、予実管理は月次で定期的に実施することが望ましいです。月次であれば、状況が悪化してしまう前に対策を取ることができるため、問題が拡大することを防ぐことができます。
洗い出された課題と改善策は現場の従業員と情報を共有し、業務改善を行うことになります。普段から情報共有する仕組みづくりをしておくと、スムーズな意思疎通が図れます。また、日頃から部門間やチーム内の風通しを良くしておき、コミュニケーションを取りやすくしておくと、課題や改善策をどのように具体化すれば良いのか、担当者同士が話し合い、実務への落とし込みもしやすくなります。
3-5 システムを活用する
予実管理では、予実管理表を作成します。経営者や従業員が目標売上高や対応すべき課題を共有することは、予実管理の重要なプロセスになります。
予実管理表については、初めて予実管理を行う場合はExcelを使って作成されるケースが多くあります。また、個人事業主や中小企業、単一の事業内容、グループ会社がないなど、数字の集計が簡易な場合は、引き続きExcelを使って予実管理表を作成している会社は少なくありません。
一方で、徐々に会社の規模が大きくなり、事業内容が複雑になってくると、予実管理表をExcelで作成するのが難しくなってきます。経理部や経営企画部の担当者が予実管理表の作成にかける労力が大きくなり、負担になってくるでしょう。マクロや複雑な計算式を駆使する必要が生じるため、Excelに詳しい担当者に作業が偏り、業務の属人化が進みます。
Excelでの予実管理に限界を感じているようなら、予実管理の効率化をはかるためにも、システムの活用を検討するタイミングです。システムを使うことで、業務の効率化がはかれると共に、ミスを防ぎ、またスピーディに予実管理表が作成できるようになります。
4 予実管理に役立つシステム
予実管理の重要性は理解しているが、経営資源は限られているので、なるべく効率的に導入したいという企業が多いのではないでしょうか。以下では、予実管理に役立つさまざまなシステムをご紹介します。
4-1 Excel
 Excelはパソコンを使って仕事をしている人なら、一度は使ったことがある身近なソフトウエアです。管理部門の人なら誰でも扱えるという理由で、予実管理表をExcelで作成している企業も多くあります。
Excelはパソコンを使って仕事をしている人なら、一度は使ったことがある身近なソフトウエアです。管理部門の人なら誰でも扱えるという理由で、予実管理表をExcelで作成している企業も多くあります。
ただし、Excelは誰もが利用できる反面、複雑な計算式を使用したり、マクロを駆使したりすると、極めて複雑なフローになってしまうデメリットがあります。
予実管理表を作成するためには、部門ごとの金額を集計したり、商品別の売上を集計したり、間接部門の発生費用を配賦したりと複雑な計算が必要です。最適な予実管理表をつくりたいと思うと、マクロを組み込んだり関数を使用したりと、ある程度の作り込みが必要でしょう。結果として作成担当者には高いレベルでのExcelの知識が求められることになります。
こうしたことから懸念されるのが、業務フローの属人化です。人事異動や入退社により、予実管理表の作成担当者の交代などの場面で、混乱することが予想されます。
4-2 Googleスプレッドシート
Excelと基本的な機能が同じで、リモートワークの普及に伴い利用が拡大しているのがGoogleスプレッドシートです。
予実管理表の作成には大きく2つの課題があります。1つ目は他部門や子会社のデータを集計するので、転記やデータ結合の手間がかかること。2つ目は、最適な予実管理表をつくるためには、複雑な計算式やマクロなどを駆使する必要があることです。
まず1つ目の転記の手間がかかるという点ですが、Googleスプレッドシートは他部門や子会社の担当者と共有しやすく、複数人で1つのファイルを同時編集できることがメリットとなります。
2つ目の複雑な計算式やマクロを組むことが必要という点ですが、Excelでは使えるけどGoogleスプレッドシートでは使えない関数があります。そのため、Googleスプレッドシートでは使えない関数を使用する場合には、Excelの方が使い勝手が良いという結果になります。
ただ、Excelの方がなじみがあって使いやすいという理由で、共有や集計の時だけGoogleスプレッドシートを使い、作業はExcelで行うという使い方もしている企業もあるようです。
また、GoogleスプレッドシートはExcelと同様に、属人化のデメリットがあります。
5 予実管理を効率化させるSactona(サクトナ)
以上、予実管理についてお伝えしました。予実管理は経営に直結するマネジメントのひとつです。自社の状況を定量的に把握することができ、経営課題の発見に結びつく予実管理の実施は、企業をさらにスケールアップさせることにつながるでしょう。
予実管理表の作成にExcelやGoogleスプレッドシートを使用しているものの、その限界を感じている企業も増えてきています。その理由としては、業務の複雑化や人材不足が深刻化する中、管理業務の効率化や属人化の排除が必要不可欠になったことが挙げられます。
アウトルックコンサルティング株式会社では、インターフェースはExcelやGoogleスプレッドシートのまま、一方で属人化を防ぎ、社内の他システムとデータ連携するエンタープライズソリューションである『Sactona(サクトナ)』を提供しています。
また同社では、お客様の業務やニーズに合わせて、帳票設計を含むアプリケーションをSactona上に構築するコンサルティングサービスを提供しており、経営管理システムのすみやかな導入が可能になります。